第60回水環境懇話会 議事録
蛯江 美孝氏
国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環領域 上級主幹研究員
第60回水環境懇話会では、国立環境研究所の蛯江美孝氏をお招きし、分散型インフラとしての浄化槽の技術開発動向と今後の展開について紹介いただいた。その後の質疑応答では参加者との活発な意見交換が行われた。
1. 経歴紹介
2004年国立環境研究所入所。浄化槽をはじめとした生活排水処理システムの高度化や資源循環技術に関する研究に携わり、現在は浄化槽分野における温暖化対策や海外展開について研究を進めている。また、日本水環境学会や廃棄物資源循環学会、国際水協会等に所属し、生活排水、生ごみ、汚泥等の対策や温室効果ガス排出量の削減等に関する研究に取り組むとともに、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)、ISO(国際標準化機構)、JICA(国際協力機構)等のプログラム等に携わる他、浄化槽関係の委員会の委員などを務める。
2. 講演内容
① 浄化槽の技術的変遷
- 浄化槽は合併処理浄化槽と単独処理浄化槽に大別される。
- 合併処理浄化槽は水洗トイレの排水と、台所、風呂洗濯などの生活雑排水を併せて処理する方式。
- 単独処理浄化槽では水洗トイレの排水のみを処理し、その他生活雑排水は未処理で放流する方式。
- 単独処理浄化槽は放流水の水質に係る技術上の基準において、BODが90 mg/L以下と、性能が合併式(20 mg/L以下)と比べて低く、さらに生活雑排水が未処理で放流されるため、平成13年4月1日以降新規設置が禁止されている。
- 浄化槽の特徴としては以下の通りである。
・浄化槽は5人槽から数万人槽まである。
・排水の発生する場所と処理する場所が極めて近いことから、地域の水の涵養という観点で大きな長所あり。
・建物の利用者が水を捨てたときにのみ浄化槽に排水が流入してくることから、流入に大きな変動がある。そのため、小さな装置で排水処理性能を安定的に維持する上で大きなハードルがある。
・排水に含まれる固形物や余剰となった汚泥を槽内に長期間貯留する。数か月に1回の保守点検で性能を維持する。
- 浄化槽の技術開発動向としては高度処理タイプ、膜分離タイプ、コンパクトタイプの開発が進められてきた。
- これまでは建築基準法に基づく告示により示された構造例示型浄化槽のみが設置されており、どのメーカーも似た構造であったが、2000年から性能評価型浄化槽が販売できるようになり技術開発が進んだ。
- 小型の浄化槽では生物膜法(接触ばっ気)が主流。波板状接触材が主だったが、性能評価型が出てから担体流動法も開発された。
- 性能評価型浄化槽では、同じ処理性能でも構造例示型よりコンパクト化されており、例えば5人槽において構造例示型では約3m3であるのに対して、1.5m3未満の製品も登場している。
- 浄化槽の電力消費は、ほぼブロワによるもの。ブロワ自体の消費電力削減の他に、処理方式や散気方法などの改良によって必要とする風量を減らすなどの省エネ化が進められている。
- 今後の展開としては以下の通り。
・固形塩素剤に変わる安定的な消毒方法として、紫外線(UV-LED)による消毒技術の開発が推進されている。ただし現行の法定検査では消毒効果の確認に残留塩素を測定していることから、関係法令の改正も重要。
・近年、汚泥炭化で得られるバイオチャーの農地還元がCO2削減策として注目されている。排水処理由来の温室効果ガス削減が難しい中で、浄化槽汚泥の炭化技術開発がCO2オフセットに貢献可能。
・槽内へのWebカメラの設置により、AIも活用した浄化槽の維持管理業務の効率化・高度化が試みられている。
- 日本の浄化槽技術は新製品の開発サイクルが短く、他の先進国の小規模分散型排水処理槽と比較して遜色ないどころか、コンパクトで高性能な製品になっている。
- 定期的な保守点検や汚泥の引き抜きは人材不足もあり、実施率が高くない。IoTやAIの技術の活用を含め、いかに適切に運用していくかが重要。
② 特定既存単独処理浄化槽
- 2020年に施行された改正浄化槽法により、「そのまま放置すれば生活環境および公衆衛生上重大な支障を生ずるおそれがある状態にある既存の単独処理浄化槽」を「特定既存単独処理浄化槽」と位置付けられた。
- 改正浄化槽法の制度の活用促進に向けて浄化槽法施行状況点検検討会が発足され、特定既存単独処理浄化槽の判断の明確化による合併浄化槽への転換が促進されている。
③ 浄化槽からの温室効果ガス排出量の算定
- 浄化槽におけるメタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)生成プロセスは解明されてきている。
- 生活排水処理分野における非エネルギー起源GHGs(CH4、N2O)排出に対し、浄化槽の影響は大きい。
- 温室効果ガスインベントリの作成に用いられる汲み取り便槽の排出係数は、改訂前は単独処理浄化槽の排出係数を代用しており、実測等の調査は行われていなかった。
- 国立環境研究所を含むグループは、浄化槽の技術開発が進んだことも踏まえた浄化槽の温室効果ガス排出係数の正確化を進めるため研究を行った。また、これまで科学的知見のなかった汲み取り便槽についても温室効果ガス排出実態を明らかにした。
・排出源として浄化槽、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)、汲み取り便槽(無臭便槽・簡易水洗)を対象とした。
・調査の結果、新たな排出係数は汲み取り便槽は改定前より低くなったが、浄化槽、みなし浄化槽については改定前より高くなった。
・改定後の排出係数による排出量の正確化を行ったところ、全体的に排出量は増加したが、排出量が経年的に減少していくトレンドに変わりなかった。
・汚泥清掃時を模擬した試験も行ったところ、清掃時は汚泥が撹拌され、CH4、N2Oともに濃度が上昇したが、1時間以内に通常濃度まで低下したことから、汚泥清掃の頻度が年1回ということも考慮すると、清掃時の排出量は浄化槽からの全体排出量の0.1%以下と非常に小さいものと考えられた。
④ 世界の動向
- SDGsでは2030年までに未処理の下水の割合半減を目標にしており、途上国では下水道(集合処理)が普及しない中、浄化槽が代替手法の一つとなりうる。
- ジャカルタ、バンコクでは下水道整備マスタープランが作られているものの、コスト、工期等が課題で進んでいない。
- 講演者らは東南アジアにおける小型排水処理装置の普及を目指した調査研究を実施しており、特にインドネシアにおいて現地調査や処理装置の性能評価の仕組みづくりに関する取り組みを実施してきた。
・インドネシアの下水道整備率は3%程度であり、セプティックタンクという一次処理のみの分散型処理システムが多い。
・2016年に、政府はより厳しい排水基準を策定したが、この基準を順守するための仕組みが不十分であった。具体的には市場の製品がカタログ通りの処理性を有していることを適正かつ公平に判断する方法がないなどの問題があった。
・そこで、産官学のステークホルダー会合を主催し、製品の性能評価手法と認証制度を検討し、最終的に国家規格(SNI 9161:2023)の制定に至った。
・性能評価手法の検討にあたっては、実際に現地の戸建て住宅での調査も行ったが、インドネシアは生活習慣の違いにより、日本よりも排水量変動のピークが低く、温度も高いためばっ気量が少なく済み、浄化槽導入の技術的ハードルは高くないと考えられた。
3. 質疑応答
- 3か月ごとに定期点検ということだったが、その間に問題が発生したらどう気づくのか、どう対処するのか。
⇒詰まりや漏水など、何らかの異常が発生しないと問題に気づけない仕組みである。クレームが発生した時点で大きな問題となるため、現状では未然に問題を発見し対応することは困難である。浄化槽は小型で多数設置されているため、個別の監視が難しいという背景がある。
- 特定既存単独処理浄化槽を実際に国が撤去しようとした事例はあるか。
⇒国が撤去まで行った事例はない。ただし、行政が特定既存単独処理浄化槽と位置付けた事例は存在する。その場合、直ちに撤去が義務付けられるわけではないが、改善の方向へ進んだ事例は少ないながらもある。
- すべての単独既存浄化槽が指定されているのか。
⇒すべてが指定されているわけではない。重大な支障が生じる恐れのある状態のものを見極めて指定する。従って、合併処理浄化槽であっても同様の状態であれば問題とすべきである。なお単独処理浄化槽は現在製造されておらず、古いものが多い。
- 下水道施設のダウンサイジングが必要になってきている。地方部においてダウンサイジングの受け皿として個別処理は魅力的である。ダウンサイジングを意識した新たなタイプの浄化槽の開発の動きはあるか。
⇒下水処理から浄化槽への切り替え時に求められる要件が明確になっていない。現在、下水道から浄化槽への切り替えを積極的に推進しているわけではない。複数世帯の排水処理が可能な「共同浄化槽」のような仕組みは開発されているが、まだ普及段階にあり、これが解決策となるかは不明である。
- 敷地が狭い家に新たな浄化槽を作る際など、サイズが小さい浄化槽が求められているのでは。
⇒現在の浄化槽はすでに小型化が進んでおり、これ以上のコンパクト化は難しいと考えている。既存の浄化槽を入れ替える際も、これ以上のダウンサイジングは困難である。ただし、汚泥清掃の頻度を高めることで小型化できる可能性はある。
- 分散型の水道の分野では、使用されなくなり放置された設備が問題になることがあるが、浄化槽についてはどうか。
⇒浄化槽において、使用されなくなった場合には清掃を実施した上で廃止届を出すことになっているが、実際には適切な届けが行われていないことも多い。行政による把握は進んでいないが、清掃業者が実態をよく把握しているケースが多い。近年は協議会が設立され、情報共有やデータ管理の取り組みが進められている。
- インドネシアの浄化槽導入の経緯の評価は行っているのか。
⇒インドネシアではモデル設置を進めてきたが、数年後には稼働していない事例も見られた。普及には至っていないのが現状である。過去10~15年の普及状況を考えると、ビジネスベースで進む仕組みでなければ定着は難しいと認識している。現地のルール変更や、海外に進出している日本企業の協力も必要である。日本の浄化槽は知名度があるが、価格が高いという印象が強く普及が進んでいない。単に安価にするだけでなく、浄化槽の必要性に対する優先順位を高め、理解を深めてもらう必要がある。資金力のあるリゾート地など、中大規模施設から導入を進めるのが良いと考えている。
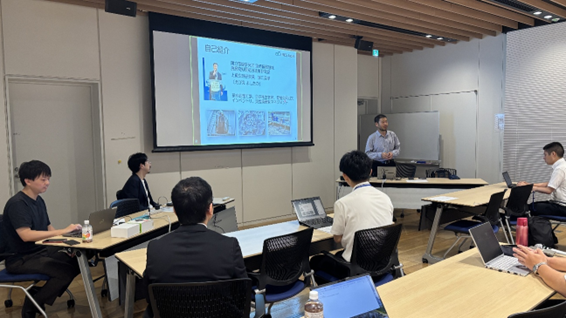

講演中の様子

